今回は、ホームページを作る理由について少し触れたいと思います。
SNSが流行る現代で、それを自身のホームページ代わりとしている人も多いですよね。
しかし、まだまだグーグルやサファリなど検索エンジンは使われていますし、SNSからホームページという流れもあります。
ホームページがあることで、事業者としての信頼度が増すことはもちろん、「24時間働いてくれる自社の営業マン」として考えることもできます。
本記事では、ホームページを持つメリットについて、信頼性の向上、SNSとの役割分担、費用対効果、そしてよくある誤解への反論という観点から解説します。
ホームページが信頼性を与える理由

個人事業主の場合、規模が小さい分だけ信頼を得にくい傾向がありますが、きちんとしたホームページがあるだけで「しっかり事業をしている」という印象を与えることができます。
多くの顧客はサービス選びの際にホームページの有無で判断する傾向があり、「ホームページが存在する」という事実そのものが信用の証明になるのです。
帝国データバンクの2023年調査では、取引先企業の信頼性や事業内容を調べる際、「ホームページを参考にする」と回答した担当者が約7割にのぼりました。
出典:Rushup
私も勤めていた会社の事務の方と営業電話の対応について話をしたことがありますが、電話で会社名を聞いた瞬間に会社名を検索すると話していましたね。
電話などで顔の見えない状況などでは、有力な名刺代わりにもなってくれます。
また、これは企業同士に限った話では有りません。
自身を消費者として鑑みた際にもなにか商品を買うときに、その商品について検索してみることや、販売者を検索した経験もあるのではないでしょうか?
そして、注意しなければならない点は、ホームページもあれば良いというものではなく平成初期感漂うような更新力の低いページや、内容の薄すぎるページであれば逆に相手を不安にさせてしまいます。
企業として、個人事業主として更新がしやすく見やすいホームページを持つことは、それだけで有能な営業マンを雇うことと考えてもいいでしょう。
- ホームページは24時間無休で働く営業マン
- ネット上の名刺となり信頼性を大きく高められる
- 古いホームページだと逆に不安にさせてしまう
SNSでは代用できないホームページの役割と補完関係

ホームページには、ネット上の名刺というだけでなく、情報発信の場という役割もあります。
「情報発信こそ、SNSで十分では?」と思う方も多いかもしれません。
ここでは、ホームページとSNSの明確な違いや棲み分けについて触れてみましょう。
プラットフォームの安定性
SNSは手軽に始められて拡散力もありますが、特定のプラットフォームに依存するリスクがあります。
運営会社の方針変更やアルゴリズム次第で、せっかくの情報もユーザーに届きにくくなる可能性は避けられません。
場合によってはアカウント凍結など予期せぬトラブルで、積み上げてきたフォロワーとの繋がりを一瞬で失うリスクもあります。
一方、独自ドメインで開設したホームページは自分で管理権限を持てるため、外部プラットフォームに左右されにくいのが強みです。
情報の蓄積と検索の利便性
SNSではタイムラインの流れが速く、投稿がどんどん埋もれて過去の情報が探しづらいという特徴があります。
新しい投稿に押し流されてしまい、商品情報や告知も次々と消えていってしまいます。
これに対しホームページのコンテンツはサイト内を整理しておけば古い情報でも探しやすく、検索エンジン経由で長期間にわたりユーザーに発見され続けるというメリットがあります。
いわば、ネット上で資産として残っていきます。
かつては、「ググる」という言葉も流行りましたが、現在は「ジピル」という言葉でチャットGPTにまずは相談するという人たちも増えています。
そんな時、チャットGPTはどこから答えを持ってくるのかといえば、それは検索結果からです。
AIにも拾ってもらいやすい権威のあるサイトに育てることで、SNSでは補えない部分でしっかりとユーザーに情報を届ける事ができます。
情報の体系性と詳細な発信
SNSは速報性や拡散性に優れていますが、情報が流動的で整理されていません。
要は、固定的な情報を伝えるには向いておらず、ユーザーが知りたい関連情報をすぐに見つけにくくなっています。
その点、ホームページではサービス内容から料金体型、実績などビジネスの内容に関して体系的に伝えることができます。
1つの情報が1つのページにまとまっている状態は、検索結果としても上位になりやすく、よりユーザーに求められるページへと育っていきます。
その結果、興味を持った顧客に十分な情報提供ができることで信頼感が高まり、問い合わせから商談・契約までのハードルを下げる効果も期待できます。
こうした違いを踏まえ、ホームページとSNSは「公式情報の発信」と「拡散・顧客との交流」で役割分担するのが理想的です。
ホームページにSNSの投稿内容を載せることもできるので、併用することで、情報の体系化を図ることができ、なおかつ更新も速報性と拡散性を兼ね備えた運用ができますね。
また、今回はSNSと一括りにしていますが、SNSの種別としてXやInstagram、Facebookなどでもそれぞれ役割や得意分野が違うことにも注意が必要です。
| 項目 | ホームページ | SNS |
|---|---|---|
| 即効性 | △ | ○ |
| 拡散性 | △ | ○ |
| 情報の蓄積 | ○ | △ |
| ビジネス訴求 | ○ | △ |
初期費用をかけても元が取れる理由

ホームページの制作費は、安くても10万以上することがほとんどです。
「ホームページを作っても費用倒れになるのでは?」という心配の声もあるでしょう。
しかし、適切に活用すればホームページへの初期投資は十分に回収可能です。
むしろホームページは長期的に新規顧客を生み出し続ける資産となりえます。いくつか具体例を見てみましょう。
例えば、とある小規模企業B社では、長年チラシ配布など紙媒体で集客していましたが反応率が低下していました。
2021年にホームページを新規開設し、施工事例や料金目安、スタッフ紹介、Q&Aなど情報を充実させたところ、「地元で安心して頼める会社」として認知度が急上昇。
その結果、Web経由の月間問い合わせ件数は制作前の5件から35件以上に増加しました。また顧客アンケートでも「ホームページで事前に事例やスタッフの顔が分かり安心できた」との声が多く、成約率も大幅アップ。
現在では新規顧客の約7割がホームページ経由となっています。
このように、ホームページに情報をしっかり載せたことで問い合わせ数・成約率とも飛躍的に向上し、売上増加につながった好例です。
ネット販売をしていた個人事業主がホームページ上に返品ポリシーや利用者レビューを載せて購入前の不安を解消するページを設けたところ、カート落ち(途中離脱)率が下がり月間売上が前年比150%に伸びたという報告もあります。
これらのケースからも、ホームページの整備が顧客の安心感につながり、結果として売上増・利益増に直結することがわかります。
ホームページ経由で新規契約が1件でも取れれば充分に元が取れる可能性があります。
極端な話、仮に制作に数十万円かかったとしても、それによって獲得できた契約や販売額がそれ以上であれば投資対効果はプラスです。
「ホームページ経由の問い合わせから月に3件契約が増えた」という例もあり、初期費用を単なるコストではなく未来への投資と捉えることが重要だという指摘もあります。
サーバー代やドメイン代など多少のランニングコストはかかるものの、自社の状況に合わせて集客強化したい時期は更新を増やし、落ち着いている時期は最低限の運用にするなど柔軟にコントロールできる点もメリットです。
以上のように、ホームページへの支出は継続的な集客チャネルを構築するための投資であり、しっかり活用すれば十分に元を取ることができるのです。
- 一度作ってしまえば、ランニングコスト自体はそこまで高くない。
- 新規一件でも元が取れる可能性は十分にある。
- 適切に運用することで継続的な集客ツールになる。
まとめ
個人事業主にとってホームページを持つことは、信頼度の向上、新規顧客獲得の安定した経路、デジタル上の名刺・ポートフォリオとしての活用など、多くのメリットがあります。
特に現代の顧客はまずオンラインで情報収集するため、公式サイトがないと機会損失につながりかねません。
ホームページとSNS、オフラインでの活動を組み合わせれば相乗効果も期待でき、ビジネスの幅が広がります.
一方で、ホームページは作って終わりではなく継続運用して情報をアップデートしていくことが大切です。
最初は手間やコストがかかるかもしれませんが、それを未来への投資と捉えてしっかり活用すれば、必ずや事業成長の強力な後押しとなるでしょう。
「ホームページは必要か?」と迷っている方は、ぜひ今回紹介したメリットや事例を参考に、前向きに検討してみてください。
きっとあなたのビジネスの信頼性と可能性を高める武器になってくれるはずです。

ホームページ制作でお悩みならまずは相談してみませんか?
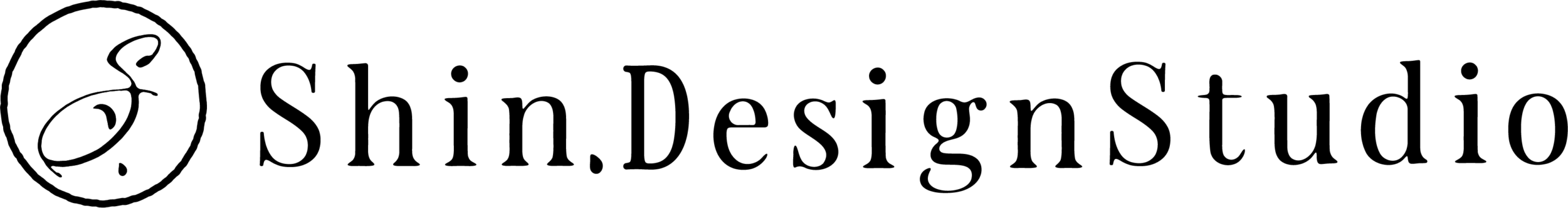



コメント