今回は、ロゴのデザインについてのお話です。
ロゴに限らずですが、デザインの価値が低く見られることはよくあります。
「そこまでデザインにこだわる意味はあるのだろうか?」「伝われば良いんじゃないか?」そう考える人も少なくありません。
しかし、売上を上げている企業や事業者は決まってロゴには力を入れています。
なかには、ロゴのデザイン費だけで億をかける企業もザラなんです。
大企業であればAppleやスターバックス、ナイキ、ユニクロなど世界の名だたる企業がロゴにこだわり、何度も改良を重ねるのには確かな理由があります。
本記事では、個人事業主こそロゴを持つべき理由から、ロゴが与える第一印象やブランド認知への効果、ロゴの種類と使い分け、ロゴデザイン費用の相場と費用対効果、そしてロゴ活用の成功事例まで、数字や専門家の意見を交えて解説します。
ロゴデザインはなぜ必要?個人事業主にロゴが必要な理由とメリット
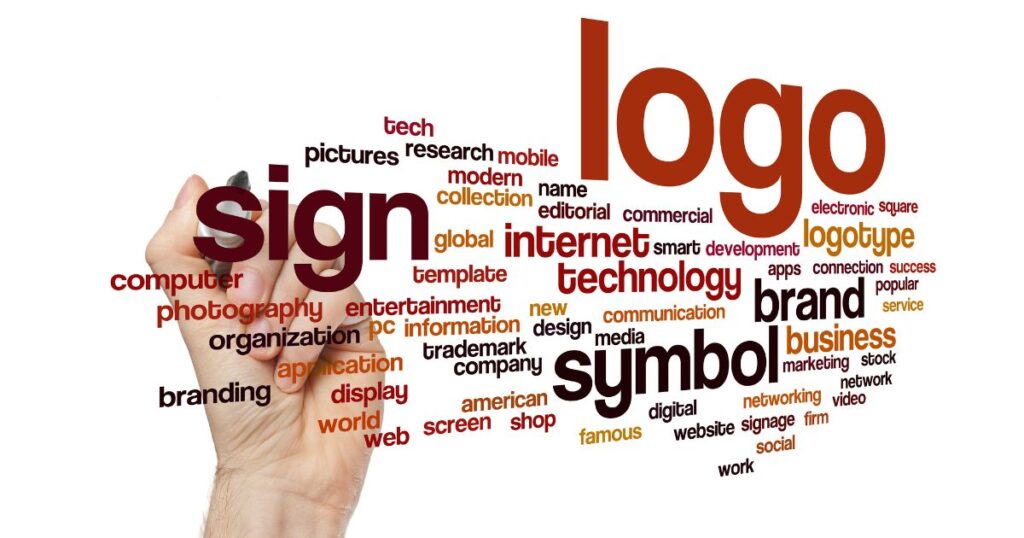
冒頭でお話したデザインについて、「伝われば良いのでは?」という話もありましたね。
これは、恋愛に例えてみると「あなたのことが好き」と言っているだけの状態。
デザインをするということは、「好き」と伝える中にも、「出会った時の感情」や「一緒に過ごした思い出」、「どんなところを素敵に感じて好きになったのか」など、色々な思いを込める工程なんです。
そしてロゴデザインはまさに顔!
告白するときに無精ひげを生やしたままですか?
何日も洗濯をしていない服を適当に着て行きますか?
しっかりとおしゃれをして、相手に思いが届くように、告白の瞬間がいつまでも相手に残るようにすることがロゴデザインです。
では、事業として改めて考えた時にメリットはどのようなものがあるでしょうか。
第一印象で信頼感アップ
人は初めて見るものをわずか0.05秒で「信頼できるか」を判断すると言われています。
スタンフォード大学の調査でも48%もの人が「会社を信頼できるかどうか」をデザインの良し悪しで判断したと報告されています。
ロゴがきちんとあるだけで「ちゃんと活動している」「しっかりしたサービスを提供してくれそう」という良い第一印象につながり、名刺やSNSで何もロゴが無い場合に比べて格段に信頼感を与えます。
そして、「画像優位性効果」といって、文字よりも圧倒的に画像や図のほうが認知されやすい傾向にあり、実体験としても感じている方は多いのではないでしょうか?
ロゴはまさに黙って働いてくれる“無言の営業マン”その顔です。
差別化とプロフェッショナル感
何度もお話していますが、個人事業主にとってロゴは事業の「顔」であり、競合ひしめく市場で自分を差別化する武器になります。
オリジナルのロゴは他社との違いを一目で示し、ビジネスに対する本気度や専門性も伝えてくれます。
ロゴマークがあることで「この会社はしっかりしている」「信用できそうだ」という印象を与えることができ、逆にロゴがないとどこか素人っぽく見えてしまうこともありますよね。
一流であるには、一流であるように振る舞うことが大切です。
プロフェッショナルでいるには、プロフェショナルなロゴを。
小さい事業ほどロゴを持つことで周囲から一段プロらしく映り、信頼獲得につながります。
覚えてもらいやすく認知向上
名前や肩書きだけより、視覚的なロゴのほうが記憶に残りやすいものです。
人が記憶する情報の約83%は視覚からと言われ、ロゴがあることで「あのロゴの人だ!」と覚えてもらえる大きな利点があります。
有名なマクドナルドも「ロゴを思い浮かべて」と言われればすぐでてくると思いますが、「綴を思い出して」と言われてなんとなく名前から連想はできますが、正確に覚えている人はあまりいないのではないでしょうか?
実際、ロゴやブランドデザインを統一して使っている企業はそうでない企業に比べ認知度が最大4倍になるとの調査結果もあります。
自身のサービスにおいて統一されたロゴ、ブランディングがされていることで関連事業でも覚えてもらいやすく効率的な認知向上に繋がります。
ブランディングと事業の成長
ロゴはビジネスの理念や世界観を象徴し、事業の核となる要素です。
ロゴがあることで名刺からホームページ、SNSに至るまでデザインの統一感が生まれ、ぶれないブランドイメージを築けます。
そして何よりも、働く従業員や自身のモチベーション向上につながるという点がとても大きいです。
しっかりと自身の想いや理念を反映させたロゴは、サービスや従業員にまで想いが電波し、質の向上にまで繋がります。
実際、ロゴやブランドに誇りを持てる社員は生産性が21%高いという結果も報告されているほどなんだとか!
将来への発展性
ロゴは作って終わりではなく、あなたの事業の成長とともに価値を増していく資産です。
長年使い続けられるロゴはそれ自体にブランドの歴史と信頼が蓄積され、例えばコカ・コーラのロゴは100年以上基本デザインを変えずに世界中で計り知れない価値を持つ資産となっています。
個人で活動していても、やがて事業が大きくなり法人化やチーム化するときにロゴがあればスムーズにブランドを継続・発展させやすいでしょう。
ロゴは未来への投資でもあり、「個人の域からブランドへ」と成長する足がかりになります。
ロゴが顧客に与える印象とブランド認知への効果
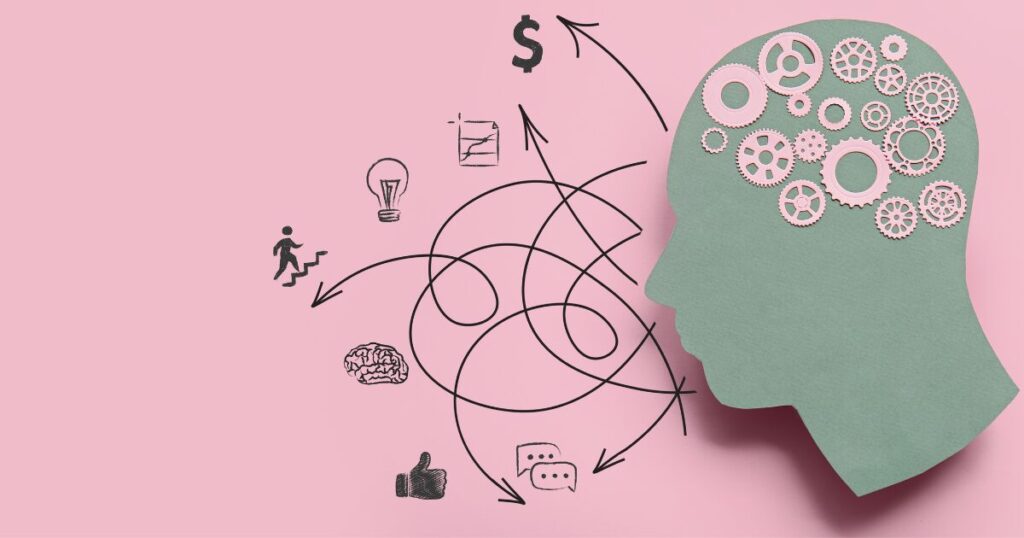
有名ブランドのロゴは一目で認識され、安心感や期待感すら生み出します。
スターバックスの緑の人魚マークは世界中どこでも視界に入った瞬間「あ、スタバだ」と分かるほど統一的に使われており、その結果「どこで見てもスタバと分かる」安心感が顧客のロイヤルティ(愛着)を高めています。
色彩の心理効果も大きく、ある調査では消費者の購買決定の約85%が色に基づいているとの結果もあります。
ロゴの色選びひとつで顧客の印象や購買意欲が左右されるのです。
例えば青は「信頼感」や「安定感」を与えるため金融機関やIT企業のロゴに多用され、赤は「情熱」や「緊急性」を連想させてマクドナルドやコカ・コーラなど食関連のロゴによく使われます。
このようにロゴの色や形は無意識下で顧客の印象形成や安心感に作用し、ブランドと顧客の関係性を深める心理的メカニズムがあるのです。
効果的で、認知を高めるロゴには、「独自の発想」がありながらも「シンプル」であることが重要です。
例えば、Amazonのロゴに描かれた矢印はアルファベットのAからZまで品揃えがあることと顧客の笑顔を表現していて、一度知ると忘れにくい“物語”を秘めています。
顧客にストーリーまで伝えることができれば、もうブランドが忘れられることは無いでしょう。
ロゴを名刺や看板、ウェブ、SNSアイコンなどあらゆる接点で一貫して使うことで「どこで見ても同じ印象」を植え付けることができ、それが長期的な記憶のフックとなって顧客の再来や紹介(クチコミ)につながります。
ロゴの種類と違い/適切な使い分け

ロゴデザインは大きく「文字(ロゴタイプ)」「シンボル(図形)」「文字+シンボルの組み合わせ」の3種類に分類できます。
それぞれメリットが異なり、事業の性質や目的に応じて使い分けることが重要です。
それでは、それぞれの特徴を見ていきましょう。
文字ロゴ(ロゴタイプ)

社名やブランド名など文字を図案化したロゴです。
例としてGoogleのロゴやコカ・コーラの筆記体ロゴ、SONYのロゴなど純粋に文字だけでデザインされたものが該当します。
文字ロゴの最大の利点は名前をそのまま読んでもらえること。
社名そのものを覚えてもらいやすく、言語の壁を越えて世界中の人にブランド名を認知させたい場合にも有効です。
例えば多国籍展開する企業は積極的にロゴタイプを採用する傾向があり、サービス名を広く浸透させたい場合に適しています。
デザイン的にもフォントの選び方で企業の個性を表現でき(角ばったフォントは力強さ、丸みのあるフォントは親しみやすさなど)、文字情報とデザイン性の両立がポイントです。
シンボルロゴ(ロゴマーク)

企業やブランドのイメージを象徴的な図形で表現したロゴです。
文字を含まないピクトグラム的なマークで、見る人に直感的な印象を与えます。
例としてAppleのリンゴマークやヤマト運輸の黒猫マーク、ナイキのスウッシュなど、マークを見るだけでどこの会社か分かるようなものが典型です。
シンボルロゴのメリットは視覚的インパクトと記憶への残りやすさです。
人はテキスト情報よりビジュアルから受ける印象の方が強いため、文字だけの場合より強烈に印象付けることができます。
例えば看板や広告でぱっと目に入った時に、社名を読むよりマークの方が瞬時に認識でき記憶に残りやすいでしょう。
加えて、シンボルがあることで「しっかりした会社」「信用できる」というイメージも与えやすくなります。
「顔を見て話した相手は記憶に残りやすい」のと同じく、企業名も顔となるロゴマークがある方が多くの人の記憶に刻まれるのです。
組み合わせロゴ(ロゴタイプ+ロゴマーク)

文字ロゴとシンボルマークを組み合わせたロゴです。
文字だけ・マークだけ双方の良さを取り入れた形で、新興の企業や小規模事業にはこの組み合わせタイプが特におすすめです。
起業したばかりの会社がロゴマークのみで展開しても社名を覚えてもらうのは難しいため、マークと一緒に社名もデザインしたロゴタイプを用意すると効果的です。
マークで視覚的印象を与えつつ文字で名前も伝えられるので、「顔(シンボル)と名前(テキスト)の両方を覚えてもらう」ことができます。
組み合わせロゴを持っていると用途に応じた使い分けも可能です。
例えば小さなアイコンや社章にはシンボル部分だけを使い、公式文書や名刺には文字部分も含めた正式ロゴを使う、といった柔軟な運用ができます。
将来的にブランドが成長したら、徐々にシンボルだけで展開する(有名ファストフードがマクドナルドのMだけ表示するように)こともできますし、逆に最近はシンボルを無くして文字だけのシンプルなロゴタイプに移行する企業も増えています。
いずれにせよ創業当初は文字+マークのセットでロゴを作り、徐々に認知度や戦略に応じて使い分けていくのが安全策と言えるでしょう。
ロゴデザインの費用相場と費用対効果
最後に、ロゴデザインが実際にビジネスにもたらした成功例をいくつかご紹介します。国内の身近な事例を中心に、印象的な海外の例も合わせて見てみましょう。
飲食店チェーン「スターバックス」
海外発の有名事例ですが、スターバックスのロゴ戦略も参考になります。
スターバックスは創業以来、緑色の人魚(サイレン)ロゴを一貫して使用し続け、時代に合わせて細部を洗練させつつもブランドの核(緑と人魚)は崩していません。
紙カップから店舗看板、Webサイトやアプリに至るまですべて同じロゴとカラーで統一し、「どの国でも一目でスタバと分かる」ブランド体験を提供しています。
この統一感が世界中での高いブランド認知と熱狂的ファンの獲得につながり、「またあのロゴを見つけたら入店しよう」という再来店動機にも直結しています。
スターバックスはロゴ変更で失敗したGAPの例とは対照的に、ロゴの一貫性がブランド愛着を守り抜いた成功例と言えるでしょう。
スターバックスは、創業から4度ロゴを調整しています。
時代を経るにつれて、どの企業もロゴがシンプルでスタイリッシュなものになってきているのは、現在のデザイントレンドとも関係していますね。
ナイキのスウッシュマーク(通称「✔」のような形のロゴ)は、シンプルかつ力強いシンボルとしてデザイン史に残る名作です。
創業当時わずか35ドルでデザインされたこのロゴは、現在では数十億ドル規模のブランド価値を背負うまでになりました。
ナイキは社名を入れないシンボルロゴですが、世界中の誰もがスウッシュを見ただけで「NIKE」とわかります。
製品にも必ずこのロゴが大きく配置され、スポーツの躍動感と勝利の女神の翼をイメージさせるストーリーが込められています。
シンプルなロゴ一つで圧倒的な認知とブランド連想を生み出した好例です(まさに「ロゴ=ブランド」の象徴)。
ナイキの事例のように高いから良い、安いから良くないと、単純に値段で価値を図れないのは、ロゴに限らずデザインの特徴ですね。
ロゴの場合は、使用用途や範囲、ロゴがもたらすと想定される販促効果によって値段を見積もる事が多いです。
名刺や、ホームページなど個人の販促にとどまる程度であれば3万~10万程度だと思います。
大企業のようにすべての商品パッケージに印字されたり、ブランド展開の基盤や店舗全てに展開される場合には数千万から億を超えることもあります。
重要なのは、自社の理念やターゲットにマッチしたロゴを作り、それを名刺・店舗・ウェブ・SNSすべてで一貫して使うことです。
それによってお客様の記憶に刷り込まれ、口コミで「あのロゴのお店いいよね」と話題に上がるような効果も期待できます。
まとめ
人は見た目が9割なんて言葉もありますよね。
事業であれば、その見た目の大きな割合を占めるものがロゴになります。
そして、自分の顔のように一貫して事業に浸透させることで認知度は上がり、大きな効果をもたらすことにつながるでしょう。
ロゴがあることで、自身が事業に込めた想いを再認識することや、従業員に理念を伝えやすくなります。
なによりも、顧客にロゴのストーリーまで覚えてもらえることで顧客にとっても特別な存在になることができるのです。
ぜひこの機会に、ご自身の事業を象徴する「ちゃんと伝わるロゴ」について考えてみてください。
適切なロゴはあなたのビジネスが選ばれる大きな理由となり、長い目で見れば事業成長への土台となってくれるはずです。
ロゴデザインの力を味方につけて、ブランド価値をさらに高めていきましょう。

デザイン制作でお悩みなら
まずは相談してみませんか?
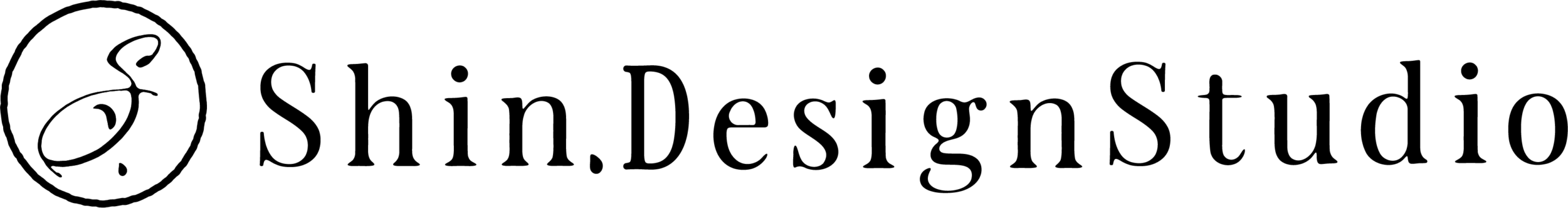


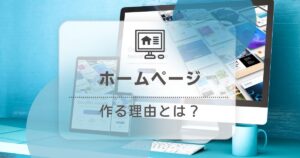
コメント